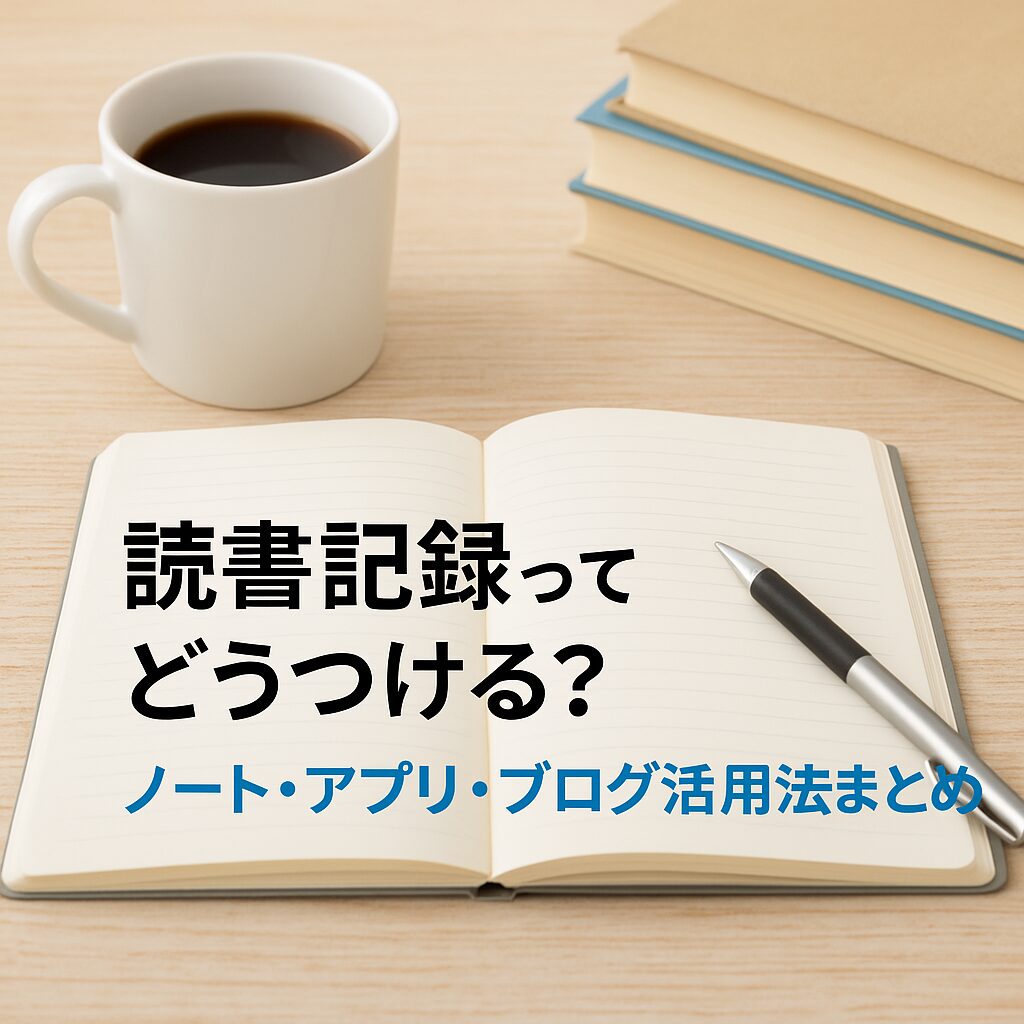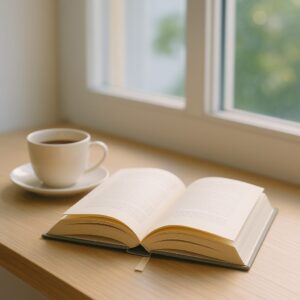本を読んでも、しばらくすると内容を忘れてしまったり、どの本をいつ読んだのか思い出せなかったり…。そんな経験はありませんか?
私自身も「せっかく本を読んでも記憶に残らない」という悩みを抱えていました。
そこで始めたのが、読書記録です。読んだ本をノートやアプリ、ブログに残すことで、振り返るのが楽しくなり、読書がより充実した時間になりました。
この記事では、読書記録をつけるメリットや、おすすめの方法(ノート・アプリ・ブログ)、さらに私自身の工夫を紹介します。自分に合った記録スタイルを見つけて、読書をもっと楽しんでみませんか?
読書記録をつけ始めた理由
本を読むのは好きなのに、気づけば「何冊読んだのか思い出せない」「内容を忘れてしまった」ということが多くありました。
また、せっかく感動した本でも、どんなところに心を動かされたのかが曖昧になってしまい、もう一度読み返すときにモヤモヤすることも…。
そんな時、「記録を残しておけば、自分だけの読書の軌跡になるのでは?」と思い、読書記録をつけ始めました。これは単なる“メモ”ではなく、後から振り返って楽しめる大切な習慣になっています。
読書記録をつけるメリット
実際に読書記録を続けてみて感じたメリットはたくさんあります。
- 読んだ本が一覧で見られる
積み重ねを「見える化」することで達成感が得られます。 - 振り返りが楽しい
過去にどんな本を読んで、どんなことを感じていたのかが一目で分かります。 - 成長を実感できる
数か月前の感想と比べると、自分の考え方や感じ方の変化に気づけます。 - 読書習慣が定着する
記録を残すことで「読みっぱなし」にせず、次の本を手に取るきっかけにもなります。
おすすめの記録方法3選(ノート・アプリ・ブログ)
① ノートでの手書き読書記録
紙に書くことで思考が整理され、心に残りやすくなります。
絵を描いたり、付箋を貼ったり、自分だけの読書ノートを作るのも楽しいポイント。アナログ派の方や、文字を書くのが好きな方におすすめです。
② 読書管理アプリ(例:読書メーター)
スマホひとつで手軽に記録できるのが大きな魅力。タイトルや著者名の検索が簡単で、感想を残したり、他の人のレビューを参考にできるのも便利です。データで整理されるので一覧性も高く、読書量を数字で把握したい人に向いています。
③ ブログでの記録(例:自分のブログ)
公開することで「誰かの参考になるかも」と思えて、モチベーションが上がります。書いた記事が検索されて読まれると、自分の記録が人の役に立つのも嬉しいポイント。発信を通じて読書仲間とつながれる可能性も広がります。
私の読書記録のルールと工夫
私自身は「シンプルに続けること」を大事にしています。
- 毎回書く項目は、タイトル・著者・心に残った言葉・一言感想
- 読み終えたその日のうちに記録する
- 書けない日は無理せず、次の本に進む
特に「心に残った言葉」をメモするルールはおすすめです。本を読み返した時、その一文だけで当時の感情や風景がよみがえることがあります。
読書記録を続けたいあなたへ
読書記録の方法に「これが正解」という形はありません。ノートでも、アプリでも、ブログでも、自分に合ったやり方を選べば大丈夫です。
大切なのは、記録することで「本を読む時間がより豊かになる」こと。最初は1行の感想だけでも構いません。小さな一歩から始めて、自分だけの読書ライフを育てていきましょう。
まとめ
読書記録をつける方法は、ノート・アプリ・ブログとさまざまですが、大切なのは「自分に合った形で続けられるかどうか」です。手書きでじっくり振り返るのも、アプリで手軽に数を管理するのも、ブログで発信してモチベーションを高めるのもすべて正解。
小さな記録でも積み重ねれば、自分だけの読書の軌跡となり、大きな財産になります。まずは気になった方法を一つ選んで、1行の感想からでも始めてみませんか?